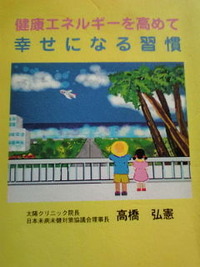2009年05月31日
ほどほどに苦、ほどほどに楽♪
今日は、東京競馬場では、
第76回 日本ダービー がありました
テレビでも中継してましたが、
皆さんはご覧になられましたか
小雨降る中でのパドックの様子が映っていましたが、
どのサラブレッドも毛艶がよく、ピカピカ光っていて、
表情も可愛いんですよね~
1着 ロジユニヴァース
2着 リーチザクラウン
3着 アントニオバローズ
という結果でした。
ロジユニヴァースの横山典弘騎手は、念願だった
ダービー初優勝だったそうです。
誠におめでとうございます
しかし、かくいう私は、
5月10日のNHKマイルの優勝馬、
ジョーカプチーノを中心に考えておりまして、
1番人気のアンライバルドにも期待しておりました
ので、惨敗でした~
雨模様で重馬場だったことも
人気馬の後退劇を手伝ったかも…
来週の日曜日は、安田記念が開催されます。
また、ガンバロウっと
はずすと、ガックリきますが、
情報を集めて分析したりしながら、
ドキドキわくわくの週末を過ごせますから、
私にとっては、小銭で楽しめる娯楽です。
さて、先日、医学講演会に行きました。
その時に拝聴させていただいたお話を
少しだけお届けしたいと思います。
「痛みの文化史」という題名で、
宮崎大学医学部付属病院 病院長の
高崎眞弓先生がお話をされました。
人の歴史は、病気との闘いの歴史でもありますが、
病気との闘いとは、治療も含めて、「痛み」との
闘いの歴史でもあります。
昔は、麻酔技術がなかったので、
治療も手術も、すべての痛みを我慢しなければ
なりませんでした。そのために、治療・手術などの痛みを
恐れて、病院から逃げ出す患者も多かったそうです。
ヨーロッパで、初めて、
エーテル麻酔が行われるようになったのは、
1846年だそうです。
一方、我が日本では、それよりも早い1804年に、
医師、華岡青洲がチョウセンアサガオなどを用いて、
乳がんの麻酔手術を成功させていたそうです。
(当時のいきさつは、有吉佐和子の小説
「華岡青洲の妻」に詳しく描かれています。)
このチョウセンアサガオですが、
昨日お世話になりました、熊本大学薬用植物園の
矢原園長先生も
「注意が必要ですよ!」
とおっしゃっておられました
山で野生のゴボウを採集する際に、形状が大変
似ているので、チョウセンアサガオの根と間違えない
ように、くれぐれも注意しなければならないということです。
自分で採集して来られて、山ゴボウと間違えて食べて、
命を落とした方もいらっしゃるそうです。
現代では、麻酔技術も発達し、私たちは、
無痛で安全な治療や手術が受けられるようになりました。
本当に、有難いことです
それは、たくさんの先人たちの
「痛みとの命がけの闘い」があったおかげなのですよね。
我慢できないほどの「痛み」とは、
私も経験しましたが、
まさに、「生き地獄」ですものね。
痛くなった時の、
お薬の使い方のポイントとしましては、
「なるべく早めに痛み止めを飲む」 ということです。
ギリギリまで我慢していて、
もう耐えられない状態になってから、
お薬を飲んでも、
なかなか効き目が現れにくいと言われています。
早めに飲んだ方が、
お薬も少量で、早く痛みが緩和される場合が多いのです。
痛みの強い病気は、様々あります。
そんな時には、
心身に負担をかけないためにも、
早くひどい痛みを取り去ることが大事だと思います。
(「痛み」には、「心の作用」も大きく関わっているそうです。
家族の存在で気分的に落ち着いたり、病院に来て安心できたり
すると、それだけで「痛み」が緩和することは、多いそうです。
だから、お母さんの「手当て」は効くんでしょうかね )
)
しかし、
「痛み」は、良い作用もしているそうです。
「痛み」を感じることができなければ、
病気になっていることにも気づかずに、
悪化させてしまうかもしれません。
また、
ある行為をした時に「痛み」を伴えば、
その人は反省し、あるいは学習して、
同じ行為をしなくなるので、
その人の進化にもつながる、ということでした。
ですが、
特に現代の日本社会では、
「快」ばかりを追求し、「苦」を避ける風潮が強いので、
そのために、
人生に深みと味わいがなくなり、
無味乾燥なものになっているのではないか?!
寒い冬があるからこそ、春が来た時の暖かさに
感謝の念や桜の花への感動の気持ちが湧いてくる。
~痛みを忘れてしまった現代文明を批判している書物~
「 無痛文明論 」 森岡正博 著
のご紹介もありました。
私も、同感です
テレビやラジオ、新聞、インターネットでも、毎日のように
刃傷沙汰の事件報道が流れています。
これは、なぜなのか?
どういうことなのか!?
時々、考えることがあります。
他者の肉体を傷つける人は、日ごろ「痛み」や「苦痛」を
感じることもなく生きてきたのではないだろうか?
私は、自分の体験から言えることがあります。
真の痛みを知った人間は、他者を傷つけることはできない。
私は、そう思います。
我慢できないほどの「痛み」にずーっと耐えることは、
心身にとって良くありませんし、
苦労をし過ぎることも、健康のためには良くないと思います。
が、楽チンにひたり過ぎるのも、良くないのかも知れません。
何事も、ほどほど、
バランスがとれているのが、一番イイのだと思います。
ほどほどに苦、ほどほどに楽
明日から、こんな感じでガンバりま~す
第76回 日本ダービー がありました

テレビでも中継してましたが、
皆さんはご覧になられましたか

小雨降る中でのパドックの様子が映っていましたが、

どのサラブレッドも毛艶がよく、ピカピカ光っていて、
表情も可愛いんですよね~

1着 ロジユニヴァース
2着 リーチザクラウン
3着 アントニオバローズ
という結果でした。
ロジユニヴァースの横山典弘騎手は、念願だった
ダービー初優勝だったそうです。

誠におめでとうございます

しかし、かくいう私は、
5月10日のNHKマイルの優勝馬、
ジョーカプチーノを中心に考えておりまして、
1番人気のアンライバルドにも期待しておりました
ので、惨敗でした~

雨模様で重馬場だったことも
人気馬の後退劇を手伝ったかも…

来週の日曜日は、安田記念が開催されます。
また、ガンバロウっと

はずすと、ガックリきますが、
情報を集めて分析したりしながら、
ドキドキわくわくの週末を過ごせますから、
私にとっては、小銭で楽しめる娯楽です。

さて、先日、医学講演会に行きました。
その時に拝聴させていただいたお話を
少しだけお届けしたいと思います。

「痛みの文化史」という題名で、
宮崎大学医学部付属病院 病院長の
高崎眞弓先生がお話をされました。
人の歴史は、病気との闘いの歴史でもありますが、
病気との闘いとは、治療も含めて、「痛み」との
闘いの歴史でもあります。
昔は、麻酔技術がなかったので、
治療も手術も、すべての痛みを我慢しなければ
なりませんでした。そのために、治療・手術などの痛みを
恐れて、病院から逃げ出す患者も多かったそうです。
ヨーロッパで、初めて、
エーテル麻酔が行われるようになったのは、
1846年だそうです。
一方、我が日本では、それよりも早い1804年に、
医師、華岡青洲がチョウセンアサガオなどを用いて、
乳がんの麻酔手術を成功させていたそうです。
(当時のいきさつは、有吉佐和子の小説
「華岡青洲の妻」に詳しく描かれています。)
このチョウセンアサガオですが、
昨日お世話になりました、熊本大学薬用植物園の
矢原園長先生も
「注意が必要ですよ!」
とおっしゃっておられました

山で野生のゴボウを採集する際に、形状が大変
似ているので、チョウセンアサガオの根と間違えない
ように、くれぐれも注意しなければならないということです。
自分で採集して来られて、山ゴボウと間違えて食べて、
命を落とした方もいらっしゃるそうです。
現代では、麻酔技術も発達し、私たちは、
無痛で安全な治療や手術が受けられるようになりました。
本当に、有難いことです

それは、たくさんの先人たちの
「痛みとの命がけの闘い」があったおかげなのですよね。

我慢できないほどの「痛み」とは、
私も経験しましたが、
まさに、「生き地獄」ですものね。
痛くなった時の、
お薬の使い方のポイントとしましては、
「なるべく早めに痛み止めを飲む」 ということです。
ギリギリまで我慢していて、
もう耐えられない状態になってから、
お薬を飲んでも、
なかなか効き目が現れにくいと言われています。
早めに飲んだ方が、
お薬も少量で、早く痛みが緩和される場合が多いのです。
痛みの強い病気は、様々あります。
そんな時には、
心身に負担をかけないためにも、
早くひどい痛みを取り去ることが大事だと思います。
(「痛み」には、「心の作用」も大きく関わっているそうです。
家族の存在で気分的に落ち着いたり、病院に来て安心できたり
すると、それだけで「痛み」が緩和することは、多いそうです。
だから、お母さんの「手当て」は効くんでしょうかね
 )
)しかし、
「痛み」は、良い作用もしているそうです。
「痛み」を感じることができなければ、
病気になっていることにも気づかずに、
悪化させてしまうかもしれません。

また、
ある行為をした時に「痛み」を伴えば、
その人は反省し、あるいは学習して、
同じ行為をしなくなるので、
その人の進化にもつながる、ということでした。

ですが、
特に現代の日本社会では、
「快」ばかりを追求し、「苦」を避ける風潮が強いので、
そのために、
人生に深みと味わいがなくなり、
無味乾燥なものになっているのではないか?!
寒い冬があるからこそ、春が来た時の暖かさに
感謝の念や桜の花への感動の気持ちが湧いてくる。

~痛みを忘れてしまった現代文明を批判している書物~
「 無痛文明論 」 森岡正博 著
のご紹介もありました。

私も、同感です

テレビやラジオ、新聞、インターネットでも、毎日のように
刃傷沙汰の事件報道が流れています。
これは、なぜなのか?
どういうことなのか!?
時々、考えることがあります。
他者の肉体を傷つける人は、日ごろ「痛み」や「苦痛」を
感じることもなく生きてきたのではないだろうか?
私は、自分の体験から言えることがあります。
真の痛みを知った人間は、他者を傷つけることはできない。
私は、そう思います。
我慢できないほどの「痛み」にずーっと耐えることは、
心身にとって良くありませんし、
苦労をし過ぎることも、健康のためには良くないと思います。
が、楽チンにひたり過ぎるのも、良くないのかも知れません。
何事も、ほどほど、
バランスがとれているのが、一番イイのだと思います。

ほどほどに苦、ほどほどに楽
明日から、こんな感じでガンバりま~す

歯を磨いてガン予防
女性の味方の漢方製剤♪
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第5回)
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第4回)
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第3回)
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第2回)
女性の味方の漢方製剤♪
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第5回)
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第4回)
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第3回)
認知症ワンポイント・メモ(5回シリーズ:第2回)
Posted by noapitt at 22:39│Comments(0)
│健康情報